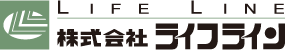ブログ・ニュース
法律上の賠償責任 と 危険の予見可能性

「法律上の賠償責任」を考えるうえで「危険の予見可能性」は重要な要素だ。
予見可能性とは、goo辞書の国語辞典によれば、
よけん‐かのうせい【予見可能性】 の解説
危険な事態や被害が発生する可能性があることを事前に認識できたかどうか、ということ。
重大な結果を予見できたにもかかわらず、危険を回避するための対応・配慮を怠った場合、過失を問われることがある。
〔引用終了〕
とされている。
さて、去る6月28日、注目の判決が言い渡された。
メディアの中でも、栃木県の地元紙・下野新聞が詳細に報道しているので引用したい。
■下野新聞電子版 6月28日12時35分
栃木県那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故を巡り、
5遺族が県や県高校体育連盟(高体連)、講習会の責任者だった教諭ら3人に計約4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、宇都宮地裁であった。
浅岡千香子(あさおかちかこ)裁判長は県と県高体連の過失を認め、計約2億9270万円の賠償を命じた。
3人については、公務員の職務で損害が発生した場合、国や自治体が賠償責任を負うとした国家賠償法の規定に基づき、請求を棄却した。
遺族側は控訴しない方針。
判決は雪崩事故の発生について、遅くとも事故当日朝の時点で気象状況などを確認していれば「雪崩発生の可能性を認識できる状況だった」と指摘。
「雪崩に対する危機意識の希薄さから、3教諭や県高体連が講習会を中止しなかったことが一因と言える」と判示した。
また事故後の対応に遅れがあったほか、講習会を続行したことについて「被災者らに落ち度は認められない」と言及した。
一方、引率教諭ら3人については、登山講習会が学校教育の一環として行われたことから「公務員の職務行為で発生した事故で賠償責任を負うものではない」として賠償請求を退けた。
死亡した引率教諭に対し、県などは自身の生命を守る判断ができたはずとして、過失相殺の適用を主張していた。
しかし判決は「引率教諭に過失は認められない」と判断した。
提訴したのは、死亡した生徒4人と教諭1人の5遺族。
雪崩発生を予見できたのに講習会を中止しなかったため、3人には重大な過失があり、事故は「人災」だと訴えた。
教諭側は国家賠償法の規定を元に訴えの却下を求めたほか、事故当日の気象情報からは雪崩発生が予測できなかったと反論した。
一方、県や県高体連は賠償責任や過失があることを認めた。
ただ、死亡した教諭は自身の命を守る判断ができたはずとして過失相殺の適用を求めていた。
〔引用終了〕
なお雪崩事故の全容について追記するならば、講習参加者は55名。
このうち、引用記事通り、生徒7名と教員1名の計8名が死亡したほか、4名が重症、3名が中等症、33名が軽症を負っている。
つまり、雪崩事故としては極めて大きな事故であったのだ。
その上でこの判決については、遺族側、県と高体連側の双方とも控訴しなかったため、判決が確定している。
他方、教諭ら3人が業務上過失致死傷罪に問われた刑事裁判は、今も係争中である。
さて、ここからは『賠償責任保険』について記述したい。
賠償責任保険と一言にいっても、その種類は多岐にわたる。
また、損害保険会社各社によっても、補償内容は様々だ。
しかし、そのような幅の広い賠償責任保険にも、概ね共通している考え方がある。
すなわち「『過失』により『法律上の賠償責任』を負った場合に補償が発動する」というものである。
(当たり前だが『故意』は免責)
この点、どこまでいっても無事故への取り組みを徹底し、事故や過失を未然に防いでいく努力を行うことは言うまでもない。
だが、そのような取り組みを経た後に発生した予期せぬ事態、つまり「危険の予見可能性」を超える事態が発生し、法律上の賠償責任を負った場合は、その賠償に見合う債務を果たしていかなければならない。
その際に有効な手段こそ、損害保険の活用である。
現代は「VUCAの時代」と言われる。
VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)を指す。
つまり私達が生きている「今」という「時」は、元々「先行きが不透明で将来の予測が困難な状態」を孕んでいるようである。
だからこそ、直面するリスクを保険料という金銭的取引により保険会社へ移転する(リスクの移転)という損害保険の基本原理を有効に活用して頂きたいと強く思う。
よく「備えあれば憂いなし」と言われるが、実際は「備えの有無が人生や会社の未来を決する」ことになる。
これが「有事」や「想定外」の本質の一つと考える。
H.Enoki