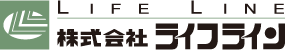ブログ・ニュース
労働災害

仕事柄『労働災害』に接することが多い。具体的には、使用者側(雇用主側)に立った労災の対応だ。
そして、そのような経験から得た私の結論は「『無事故』こそ、〝企業発展〟と
〝増収増益〟の出発点である」ということだ。
このブログを書いている時も、以下のようなネットニュースを目にした。
■静岡新聞HPより https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1189753.html
2023年2月6日
6日午後4時半ごろ、御前崎港西埠頭(ふとう)のバイオマス発電所建設現場から
「溶接作業中の作業員が倒れた」と119番があった。
建設事業を担う「御前崎港バイオマスエナジー」と御前崎市消防本部によると、
男性作業員11人が一酸化炭素(CO)中毒になったとみられ、
このうち同市池新田の会社員の男性(70)が搬送先の病院で死亡した。
残る10人のうち、55歳と43歳の男性が重症。他の2人が中等症、
6人が軽症という。菊川署は労災事故とみて調べている。
同社によると、作業員はボイラーの煙をろ過する装置「バグフィルター」の中で溶接作業をしていた。
バグフィルターは筒型の形状で、高さ約15メートル。
この日は午前8時から作業を行っていたという。
同社は「行政をはじめ関係機関と連携し、原因究明に努める」とのコメントを出した。
7日以降は建設作業を全面的に中断し、再開時期は未定という。〔引用終了〕
その上で、万が一『労働災害』が発生した際は、使用者(雇用主)に迅速かつ丁寧な対応が求められる。
この点、ここでは『弁護士法人・咲くやこの花法律事務所』の『企業法務の法律相談サービス』
(https://kigyobengo.com/media/useful/1494.html)に掲載されている西川 暢春(にしかわ のぶはる)弁護士の
記事を参照しながら、読者の皆さんと事故対応を疑似体験してみたい。
(なお引用記事は抜粋しているため、全文はホームページにアクセスして読んで下さい)
→ → → 以下、引用記事
遺族への対応
(2)補償交渉は弁護士への依頼が適切
労災保険からは慰謝料の支給はありません。
会社に落ち度がある労災事故の場合は、会社が慰謝料等を負担する必要があり、その金額を決める交渉をする必要があります。
1,賠償金額について
死亡事故で問題になる補償交渉の主な項目は、「逸失利益」、「死亡慰謝料」、「過失割合」の3点です。
(1)逸失利益について
逸失利益とは、「亡くなった本人が生きて就労を続けていれば稼いでいた金額」を損害賠償の対象とする賠償項目です。
逸失利益は労災からは支給されないため、遺族が会社に請求してくる対象になります。
そして、逸失利益は計算方法によって金額が大きく変わってきますので、その金額交渉は大きなポイントになります。
(2)死亡慰謝料について
亡くなったことについての慰謝料です。
慰謝料についても労災からは支給されないため、遺族が会社に請求してくる対象になります。
死亡慰謝料は、2000万円から2800万円くらいまでが目安となることが通常です。
慰謝料について詳しくは、以下の記事を参考にご覧ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2088.html#i
(3)過失割合について
過失割合とは、死亡事故が会社の安全配慮義務違反だけでなく、
本人の落ち度もともなって発生している場合に、本人の落ち度分を賠償額から差し引く考え方です。
労災事故では本人にも落ち度があることが多く、過失割合という形で本人の落ち度を考慮することが賠償額の交渉で重要になります。
2,賠償相手について
賠償相手は亡くなった本人の法律上の相続人全員です。
本人に配偶者や子供がいる場合は、配偶者と子が相続人になりますが、
相続人が誰かについては、本人の戸籍謄本を取り寄せるなどして正確に確認しておくことが必要です。
戸籍謄本の調査を怠って、相続人の一部とだけ賠償の交渉をしてしまうと、
あとで別の相続人から再度賠償請求されることになり、重大なトラブルとなりますので注意して下さい。
3,賠償の原資について
労災死亡事故の賠償金については1億円近くの金額になることもあれば、
過失が大きいなどの理由で1000万円にも満たない結果になることもあります。
会社で労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険に加入している場合は
保険を原資とすることができる可能性がありますので、保険会社への確認が必要です。
〔引用終了〕
このあと西川弁護士は『刑事罰を問われる可能性』について、次のように指摘している。
→ → → 以下、引用記事
3,労働基準監督署、警察での取り調べの対応
労災死亡事故については労働基準監督署や警察の事情聴取が行われます。
その結果、会社や事業主、工場長、現場責任者に刑事罰が科されるケースがあります。
また、刑事罰とは別に労働基準監督署から指導や是正勧告を受け、是正報告書の提出を求められることがあります。
(1)想定される刑事罰の内容は?
労災死亡事故で想定される刑事罰としては、主に業務上過失致死罪(刑法第211条)と労働安全衛生法違反があります。
業務上過失致死罪は個人のみが対象ですが、労働安全衛生法違反は法人も対象になります。
〈中略〉
(2)事情聴取では誘導に注意
労働基準監督署や警察の事情聴取は後日の刑事裁判における重要な証拠になります。
そのため、以下の点に注意する必要があります。
1,知らないこと、記憶にないことは話さない
まず、知らないこと、記憶にないことを推測で話してはいけません。
十分に注意して、推測を交えず、実際に体験した事実のみを正確に話すことが必要です。
2,捜査官の誘導にのって間違ったこと、あやふやなことを言わない
事情聴取をする捜査官の側は、事件を立件するために、事情聴取の対象者の答えを、
捜査側の意図に沿うように誘導しようとするケースが少なくありません。
しかし、捜査官の誘導にのって、間違ったことやあやふやなこと、
実際には体験していないことを話すことは絶対に避けなければなりません。
3,事実と違う調書に捺印しない
事情聴取の最後に供述調書への署名、捺印を求められます。
この供述調書は、刑事裁判の重要な証拠になるものですので、よく確認し、
少しでも間違いがあれば遠慮せずに必ず訂正を求めることが必要です。
また、もし、間違いがあるのに供述調書を訂正してもらえない場合は、
供述調書への署名、捺印を拒否することが必要です。
4,事情聴取の内容はすぐに書面で会社に報告する
事情聴取を受けた従業員には、その際の受け答えをその日のうちに書面にまとめ、会社に報告させてください。
このように事情聴取を受ける従業員から書面で報告を受けておくことで、
会社として捜査側の意図を把握し対応を練ることができます。
また、捜査側が労働安全衛生法のどの条文での処罰を検討しているのかという点を把握することにもつながります。
事情聴取は通常関係者複数人に対して行われますので、このように書面で記録を残しておかないと、
誰が何を聴かれてどのような受け答えをしたのかを会社として把握することが難しくなります。
〔引用終了〕
以上、今回は〝労災事故の対応〟について、疑似体験という形で考えてきた。
この点、日々の業務を遂行するうえで、『無事故』であること、そして、日頃から
『万が一に対する万全の備え』をしておくことが、重要であることが解る。
最後になりますが・・・
もしもこのブログをご覧になられて、『ふっ』と思い立たれたならば、
お気軽にご連絡下さい。
私たちが全力でお手伝いをさせて頂きます。
H.Enoki