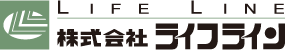ブログ・ニュース
ウイルスへの挑戦と応戦
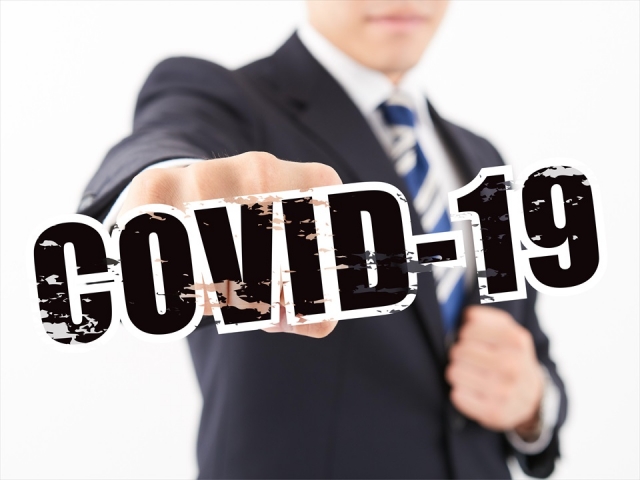
人類と感染症の関わりの歴史は古い。例えば、エジプトのミイラからは痘そう(天然痘)に感染した痕が確認されている。
ウイルスや細菌の誕生が人類の誕生以前の出来事であったことを想起すれば、人類の誕生とともに感染症との闘いの歴史が始まったといっても過言ではないだろう。
中世ヨーロッパにおいて人口の3分の1が死亡したといわれるペスト、世界中で5億人以上の者が感染し、死亡者数が2,000万人とも4,000万人ともいわれる1918年(大正7)年からのインフルエンザの汎流行(パンデミック)(「スペイン風邪」)など、感染症は多くの人類の命を奪ってきた。
〔平成16年版 厚生労働白書〕
アメリカが誇るロックフェラー大学の教授として活躍し、1982年に逝去したルネ・デュボスという細菌学者がいた。
微生物学者として出発し、世界を一新した抗生物質の研究に尽力し、「細菌生態学」という新しい分野で数多くの業績を挙げた学者である。
生化学者、医学者、結核専門医、文明批評家、環境学者など、多彩な分野で活躍し、その著書は「ピュリツァー賞」にも輝いている。
さて、このルネ・デュボス博士であるが、生物としての人間の本質について、次のような示唆を残している。
「健康な状態とか、病気の状態というものは、環境からの挑戦に適応しようと対処する努力に、生物が成功したか失敗したかの表現である」(木原弘二訳『人間と適応』みすず書房)
つまり健康とは、何の問題もない「安息な状態」を指すものではない。
むしろ、気温の上下、ウイルスや細菌の流行など、険しい環境の変化に対応して、生き抜こうとする人間の生存力が生み出した結果ということだ。
他にも、何千年という人類の歴史から俯瞰すると、現代では、過酷な自然環境である砂漠や熱帯雨林、高地などで、人類が穏やかな生活を送っていることについて、「この事実こそ人類が自然環境に適応してきた証しである」として、次のように主張する。
「常に変化を続ける環境に対して、人間は自ら適応しようと闘ってゆかねばならない」
「これは生きものすべての宿命であり、生命の法則でありまた本質そのものである」(長野敬・新村朋美訳『生命の灯』思索社)
2020年のコロナ渦は、私達の生活様式を一変させた。
私個人も、初めて1カ月に及ぶ在宅勤務を経験した。
その変化に対する試行錯誤は、今なお現在進行形で続いている。そして、その受け止め方も千差万別だ。
しかし、先ほどのルネ・デュボス博士の指摘から考えると、そんなことは〝今に始まったこと〟ではなく、長い人類の歴史の中で〝かつてから何度も繰り返されてきたこと〟ということである。
しかも、その度に人類は「ウイルスの挑戦に応戦」して、個人も社会も共に、新たな進化を遂げてきた。
加えて言えば、その度に〝新たな幸福感〟〝新たな価値観〟を見出してきたのである。
ウィズコロナ(with-corona)、アフターコロナ(after-corona)、ポストコロナ(post-corona)、という言葉ばかりが先行している。
各保険会社が主催する「オンライン会議」や「オンラインセミナー」が一気に過熱してきたことも、新しい(New)常態(Normal)への模索を感じる。
私自身も急激な環境の変化に、戸惑いを感じないと言えばウソになる。
ともあれ私としては、そのような変化も常に「ポジティブ」を真ん中におきながら、受けとめていきたい。
それは、お客様が営業マンに期待する話題は、想定外の変化について「世をはかなむ」愚痴の類ではないからだ。
お客様が営業マンに期待する話題は、この変化をどうやってチャンスに変え〝新たな幸福感〟〝新たな価値観〟を見出していくかについての「知恵」と「情報」の提供である。
そして、そのことは前述の通り、冷静に考えれば、私達の祖先が〝反復してきた営み〝そのものでもあるのだ。
激動の時代。ライフラインはお客様と一緒に、新しい(New)常態(Normal)への模索を、どこまでも「ポジティブ」に挑戦していきたい・・・
H.Enoki