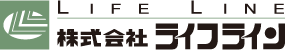ブログ・ニュース
自然災害と保険会社

商談における秋の恒例話題の一つといえば、ユーキャンの新語・流行語大賞。
その中で、トップテン入りした言葉の一つが「計画運休」。昨年に続き、観測史上最大級の台風に相次いで襲われた日本。
その影響は、鉄道各社の運行計画の在り方について、抜本的な見直しを迫る形となった。
このように、日本社会に様々な影響を与えた自然災害だが、その被害額は、ここ2年に限ってみても極めて甚大だ。
大手損保3グループによる昨年(2018年)の災害関連保険金の支払額は約1兆6千億円。今年(2019年)も1兆円規模になることは確実な見通しだ。
平時より損保各社は、大規模災害に備えて保険料収入の一部を「異常危険準備金」として積み立てを行い有事に備えている。
その異常危険準備金は2011年3月期以降、おおむね7千億~8千億円規模で推移してきた。
ところが去年・今年の自然災害の影響により、来年(2020年)3月期末には、約3850億円まで目減りする模様だ。
つまり、保険料収支の悪化は、極めて深刻なのだ。
このような状況を背景に損保各社は去る10月、火災保険料率を全国平均で6~7%引き上げた。
しかしこの料率改定には、昨年の台風21号などの支払い実績は加味されていないため、2021年にも追加して保険料を引き上げる構えだ。
「火災保険料が上がる」私達の財布にとって後ろ向きな話しも、根本的な要因は近年の急激な気候変動にある。
地球温暖化の影響で台風の数が増えたかどうかは解っていないようだが、海水温の上昇が台風の大型化や雨量に影響していることは、間違いないようである。
一時的なものではなく構造的な傾向となれば、生活におけるリスクへの備えも、同様に構造的に見直す必要がある。
なぜかといえば、それが直接的な自己防衛につながるからだ。
住宅を購入した際に加入した火災保険を、もう何年間もそのまま掛けっぱなしという方も多いと思うが、当時と現在とでは「リスク」そのものが根本的に違っていることは、前述の通りだ。
さて、火災保険は商品内容も不断の進化を続けており、最近の火災保険は、補償がバラエティーに富んでいることも特徴の一つだ。
だからこそ時々刻々の状況を正確に捉え、最適なリスクヘッジをご提案していかなければいけないとの思いを強くする今日この頃である。
H.Enoki